

開店から1年5か月の史上最速で、ミシュラン三つ星を獲得したシェフがいる。大卒で企業に務めた後、料理学校に通い、26才で仏料理店の門を叩いた遅まきのスタート。しかし塩1粒、熱0.1度にこだわる圧倒的情熱で、修業時代から現在に至るまで不可能の壁を打ち破ってきた。心を揺さぶる世界最高峰の料理に挑み続けるシェフ・米田肇のドキュメント。
フランスに生まれフランスに育ったフランス人シェフでも生涯の憧れであるミシュラン三ツ星を、なぜこの日本人は手にすることができたのか?
アンコール御礼!
トワイライトエクスプレス 瑞風で供される食事を担当する料理人の一人でもある、天才シェフ・米田肇を追ったノンフィクション『天才シェフの絶対温度 「HAJIME」米田肇の物語』の試し読みを全4回でお届けします!
* * *
「開業までの1ヶ月間はほとんど寝てません。だって、もう1年近く仕事してないわけです。力はあり余ってたし、仕事ができるってだけで嬉しくて、やりたいことがあとからあとからあふれて、一日24時間じゃとても時間が足りなかった。料理やお店のことだけじゃなくて、経営の勉強もしなきゃいけなかったから、いつもカバンの中にはビジネス書が何冊か入っていた。エレベーターに乗ってるときとか、横断歩道で赤信号を待っているときとか、ほんのちょっとした時間の隙間に読むためです。それくらい時間がなかった。もちろんまったく寝ないわけにはいかないし、妻にも心配されるから、どうして人間は眠らなきゃいけないんだろうとか思いながら、朦朧とした頭で明け方の4時にベッドに倒れ込んで、4時15分には起きて仕事を始めるみたいな生活を続けてました。肉体的には、もうふらふらです、ほんとにふらふらだった。でも、つらいと思ったことは一度もなかった」
一軒のレストランをオープンするにあたって、やらなければならないことのすべてを肇は自分でやろうとした。いや、実際にほとんどすべてを自分の手でやり遂げてしまった。
陽子は言う。
「人生の大きな決断ってあるじゃないですか。たとえば仕事を辞めるとか、何千万円という大金を借りるとか。米田はそういう大きなことに関しては即断即決というか、周囲が驚くくらいあっさり決めてしまうんです。ところがとても些細なこと、たとえばテーブルクロスをどちらにするとか、メニューの紙質をどうするとか、そういうところでものすごく悩むんです。どこかで見切りをつけて『もうどっちでもいいや』とは、絶対にならない。自分が納得できるまで、ずっと悩み続ける」
レストラン全体のプランはもちろん、壁や床の材質や色から、ホームページで使う写真の1カットに至るまで、すべてについて彼はその調子で悩み抜いたのだった。
たとえば壁の色にしても、エントランス付近と奥のダイニングでは、よほど注意深い人でなければ気づかないくらい微妙に違う色に塗られた。エントランス付近はごく微かに寒色が混ざったクリーム色で、ダイニングは微かに暖色系が強いクリーム色だった。入り口からレストラン全体を見渡したときの奥行き感を演出するためなのだが、そういう細かな工夫もすべて肇のアイデアだった。テーブルの大きさも、椅子の高さも、ミリ単位まで自分で決めた。この時期の肇は、いつもポケットに荷造り用の紐を忍ばせていた。出かけた先で、ちょうどいい大きさのテーブルや、座り心地のいい椅子に出会ったときに、その幅や高さを測るためだ。そうやって決めた彼の店の椅子の脚には、特殊な部品がついている。徹底的に研究して最適な高さを見つけたのだが、どんなに探してもその高さの椅子が見つからないので、特注で部品をつけさせたのだ。と言っても、調整した高さは数ミリでしかない。
椅子の高さの数ミリの差が、座り心地にどれだけの影響を与えるのかわからない。身長も脚の長さも人それぞれなのだから、数ミリの違いにこだわる意味はないという考え方もあるだろう。椅子の高さに正解などはないのだ。もちろん彼だってそんなことはわかっている。
けれどそれでも、答えのない問題の最適解を探して見つけた以上、その最適の高さの椅子が見つからないからといって、数ミリ低い椅子で妥協するのは、肇には敗北以外の何物でもなかった。
「95パーセントまでは誰だって努力できる」と彼は言う。みんな成功したくて努力しているのだ。95パーセントまでは誰だって努力する。けれど成功するのがほんの一握りの人でしかないのは、ほとんどの人が95パーセントで力を抜いてしまうからだ、と。
100点満点の試験で95点は悪くない、目標の95パーセントを達成すれば完成したのと同じだ。
と、普通の人は考える。
けれど、そう考える人は、いつまで経っても普通の人のままだ。
ほんとうに努力しなければならないのは、そこからなのだ。マラソンだって登山だって、ゴールの直前がいちばんつらい。そのいちばんつらい部分、胸突き八丁の最後の5パーセントでどれだけ踏ん張れるかが勝敗を左右する。
「人間の作り出すあらゆるモノのクオリティは、その最後の最後でどれだけ努力できたかで決まるんです。これで完璧だと思ったところから、さらに積み重ねた努力がクオリティの差になる。そして、その努力に終わりはない。『これで完璧だと思ったら、それはもう完璧ではない』というのは、そのことを言っているのだと思います」
こうして『Hajime RESTAURANT GASTRONOMIQUE OSAKA JAPON』は開業の日を迎える。
2008年5月12日のことだ。
スタッフは厨房4名、サービス担当3名の計7名。一緒にやりたいと言ってくれた後輩とソムリエを別にすれば、他は未経験者だった。フランス料理どころか、飲食業界そのものも初めてという若者ばかりだった。下手に経験者を揃えるよりも一からスタッフを育てたかった……と言えば格好は良いが、スポンサーも後ろ盾も何もないただの駆け出しシェフの肇が、優秀なスタッフを探してもまず見つからないのが日本の飲食業界の現実だった。
つまり彼は未経験者の集団を率いて、三つ星レストランを作ろうとしたのだ。それがどれだけ大変なことかは、彼自身もよく理解しているつもりだった。草野球チームを率いて、プロ野球の試合に出場するようなものなのだ。
スタッフは開業の1ヶ月以上前に雇用し、それぞれの職種のトレーニングを繰り返してきた。心の中で温めてきた理想のレストランの姿を話し、レストランのサービスについて語り、スペインの『エル・ブジ』やイギリスの『ザ・ファット・ダック』のように、世界中から客が来るレストランにしたいという抱負も、それを実現するための戦略や方針も語った。経験は浅くても、1ヶ月が過ぎる頃には少なくとも心構えだけは優秀なスタッフに育っていたはずだった。満を持してとまでは言えないけれど、できる限りの準備をして店をオープンしたつもりだった。
けれど、初日の客が2人だけで、しかもそれが友人だったのは、肇の幸運だった。肇が厨房にいた頃、洞爺湖の『ミシェル・ブラス』で総支配人だった人が、わざわざ大阪まで食べに来てくれたのだ。その元総支配人は「オープン初日からこんなに完成度の高い料理が出て驚いた」と感心してくれたけれど、肇には気を遣われたとしか思えなかった。料理の内容にも満足できなかったし、サービスに至っては何もかもがちぐはぐで、何一つまともにできなかった。1ヶ月の訓練期間では短すぎたのだろうか。
(「第八章 フォアグラを知らないフランス料理人見習い。」より)
※この連載は、『天才シェフの絶対温度 「HAJIME」米田肇の物語』の試し読みです。
つづきは、7月25日に公開予定です。どうぞお楽しみに!
天才シェフの絶対温度
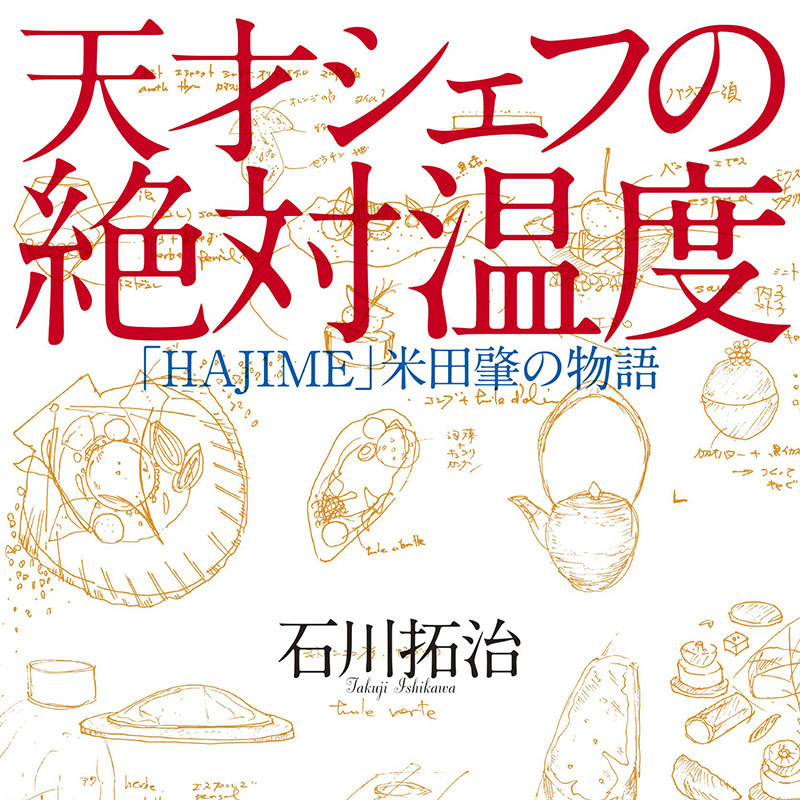
開店から1年5ヶ月の史上最速で、ミシュラン三つ星を獲得!
心揺さぶる世界最高峰の料理に挑み続けるシェフ・米田肇のドキュメント。
















