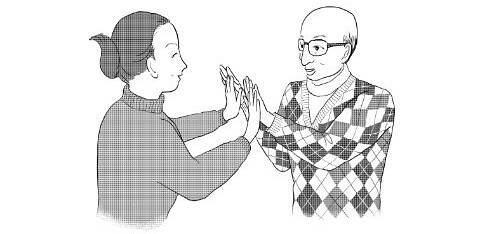コロナ禍、身近な人を亡くして、十分なお別れができなかった――という方は多いのではないでしょうか。東工大の教授(メディア論)である著者・柳瀬博一さんは87歳の父を亡くし、納棺師の女性の勧めで、突然、父親の「おくりびと」になりました。そのリアルな体験から、家族の死とどう向き合うのか? というプリミティブな感情を綴った『親父の納棺』より冒頭をお届けします。優しい挿絵は『ひぐらし日記』の日暮えむさんです。
* * *
母によれば、私と会話したあと、海外にいる妹が電話で話した。妹によれば、「こっちから一方的に話しかけただけだったけど、お父さんの息遣い、はっきり聞こえた」。そして、東京の自宅でリモートワークをしている弟と電話で話している最中に、こと切れたという。
通夜は3日後の日曜日、葬儀が4日後の月曜日に決まった。そう母は告げた。
人が死ぬと、その後の段取りは、基本的にてきぱき決まる。なぜかすぐに決まる。通夜も葬儀も待ってくれない。
うちの場合、お通夜は自宅で葬儀は地元のカソリック教会で。親父が亡くなって1時間以内に決まった。母も父もカソリックだ。私も幼児洗礼を受けている。明日金曜日には葬儀屋さんが打ち合わせに来てくれるという。
母からの電話をいったん切り、弟に電話をした。とりあえず、実家に戻ろう。
「いまから出られるか?」「出られる」「行くぞ」
1週間分の衣類とパソコンとマイクその他(Zoom用)を、フライターグのトートバッグ4つに詰め込んで車の後部座席に放り込み、近所の駅まで電車でやってきた弟を拾い、首都高速から東名高速へと走り、実家に向かった。
平日夜の東名下りは空いていた。
2020年9月以来、自動車で帰省するのは3度目だ。コロナ禍当初、県をまたいでの移動は自粛が求められていた。高速道路がずっと空いていたのもおそらくそのせいだった。そもそも他県ナンバーの車は警戒される。夜でよかった。それでも数時間かかる。
弟と直接会うのはひさしぶりだ。お互いに近況報告をする。
「おまえんところの会社、コロナ禍で儲かってるんじゃないの?」
弟は食品業界で働いている。いまは物流担当だ。
「家庭用はむちゃくちゃ売れてるね。品切れ続出。でも、外食用がゼロになったから、行ってこい、だな。兄貴、大学は相変わらずリモート?」
「完全にユーチューバー状態。大学から家に資料を持ち帰ってきたから、部屋がゴミ屋敷化してる」
「俺の仕事もリモートだね。子供も自宅学習で部屋が足りないから、トイレで会議やってる」
話が途切れる。
新東名の、トンネルと暗い山が交互に続く車窓を眺めながら、弟が漏らした。
「……親父さ、最後、なんとなく、生きる気力が失せていたような気がする」
「前もそう言ってたな」
「もう、このあたりでいいかなあ、というか。あれだけごはん好きだったのに、全然食べなくなっちゃったし」
「コロナで、家族の誰にも会えなかったしな、最後まで」
夜遅く、私と弟は実家に着いた。
親父は、ひと足先に病院から帰宅していた。
1階の庭に面した和室に。入院していたときのままの寝巻き姿で、布団に入っていた。
親父が実家に戻ってきたのは1年ぶりだ。
2020年6月に体調を崩して病院に入院し、退院するとそのまま老人ホームに入所した。再び病院に入院して亡くなるまで、自宅の敷居をまたぐことができなかった。
とりあえず声をかけた。
「おかえり」
親父は黙って寝たままだ。当然である。しゃべられても困る。
そもそも、生前の親父は、自分の話をあまりしなかった。
会話がものすごく弾むタイプでもなかった。
だから私は、親父の昔を案外知らない。
1934年、親父は浜松の下町にある建具屋の三男坊として生まれた。
釣りと野球とメンコとコマ回しと凧揚げが上手な少年だった。
なぜ知っているか。
小さい頃、全部親父が手解きしてくれたからだ。

陸軍の航空基地があった浜松は、第二次世界大戦の最中、米軍の標的となった。
1944年、浜松大空襲に遭った。さらに同じ年、東南海地震に遭い、翌1945年6月には市街地の空襲に再び遭い、親父の実家はすべて焼けた。
不幸中の幸い、家族は誰も死なず、戦後、親父は地元の商業高校に進学した。成績は悪くなかったようだ。算そろ盤ばんと習字が得意だった。
地方都市の三男坊が大学に気軽に行ける時代ではなかった。高校を卒業して、地元の銀行に就職した。
10年後、上司からの紹介で、同じ銀行の別の支店に勤めていた母とお見合いし、結婚した。親父29歳。母22歳。1年後、私が生まれ、そのあと弟が生まれ、さらにそのあと妹が生まれた。
静岡から横浜、東京、茅ヶ崎、名古屋と転勤をくり返し、静岡に戻ってきた。
銀行員としてはけっこう優秀だったのだろう。高卒にもかかわらず、複数の支店の支店長を務めた。
子供3人を東京の大学に送り出し、数年後、銀行を定年退職し、取り引きのあった建設会社の顧問となった。
親父はもともと無宗教だった。カソリック信者である母親の影響で、銀行を退職してから洗礼を受けてクリスチャンになった。毎週日曜朝、熱心に教会に通っていた。
町内会の仕事もこなし、銀行退職の前後で自動車免許を取り、車で海や川に釣りに出かけ、近所の農園で野菜づくりを楽しんでいた。
70代後半になると何度か体調を崩した。年相応だろう。ときには入院する羽目にもなったが、基本的には大病もせず、台地の縁の住宅地の一角で、母と二人で暮らしていた。近所には親戚もいるし、友人もいる。悠々自適というやつだ。
私と親父との関係は、というと、わりとあっさりしていた。
仲は悪くない。べたべたもしない。ま、普通だ。
お盆や正月に実家に帰れば、一緒に外食に行くし、東京から電話をすれば、普通に話をする。孫たちには自分をグランパと呼ばせていた。おじいちゃんと呼ばれたくなかったようだ。昭和ヒトケタの戦前生まれの男性の典型として、カジュアルに会話できるタイプじ
ゃなかったが、釣りを教えたり、畑仕事を一緒にやったりしていた。
私が健康な状態の親父と最後に過ごしたのは、2020年2月末のことだった。ほんのひと月前の正月には帰省して、高校の同窓会に出たりしていた。
にもかかわらず、わずか1ヵ月後のこのタイミングで帰郷したのには理由があった。
コロナだ。
ちょうど新型コロナウィルスに対する不安が急速に社会全体に広がりつつあったのだ。
日本では横浜港に寄港したダイヤモンド・プリンセス号で多数のコロナ患者が発生し、市中感染者も現れていた。コロナウィルスの発生源とされた中国・武漢市ではロックダウンが行われ、ゴーストタウン化した街の映像がテレビで流れた。
同時期、私は大学の試験監督業務に従事していた。試験会場は異様なほどの緊張感に包まれていた。マスクを大量に用意し、何度も消毒液を手にすり込んだ。
感染拡大が止まらないと日本も武漢同様いつロックダウンになってもおかしくない。もしそうなると、86歳の親父と79歳の母は、それほど田舎ではない静岡でも、かなり不便な状況に陥る。近所に自分の子供たちが誰もいない。私と弟は東京、妹は海外である。両親ともすでに自動車免許を返納している。つまり、買い物の足がない。家の徒歩圏にある買い物スポットはセブン−イレブンだけだ。
コロナの感染拡大で、移動も買い物もままならなくなる。私たち子供が帰省するのも困難になるはずだ。足=車を持たない老人家族は兵糧攻め状態に陥るおそれがある。いまの言うちにサポートできることはしておこう。
というわけで、私は一人で実家に戻った。
2020年2月29日土曜日の朝、ラジオのレギュラー番組の収録仕事を済ませたのち(こちらも自宅でZoom収録である。コロナが教えてくれたのは、世の中にはリモートで済む仕事が実にたくさんある、ということだ)、自動車で東京から帰省した。
家に着いたら、親父を自宅に残し、母と買い出しだ。
まずは、マスクや消毒液の確保である。市内のショッピングモール、ドラッグストアを回った。どこの店でも、マスクも消毒液もトイレットペーパーもボックスティッシュも棚が空っぽだった。すでにコロナ禍の波、いや、その前にパニックの波が訪れていた。
半日かけてさまざまな店を車で回り、老人二人が使うにはじゅうぶんなマスクと消毒液、トイレットペーパーやボックスティッシュを確保し、家に戻った。
私がスパゲティナポリタンをつくって、親父と母と一緒にビールを飲む。
夜、親父が歌を披露してくれた。母が、親父のボケ防止に、毎晩うたっているそうだ。
最初に「知床旅情」をうたい、次は「琵琶湖周航の歌」である。
われは湖うみの子さすらいの
旅にしあればしみじみと
昇る狭さ霧ぎりやさざなみの
志賀の都よいざさらば
松は緑に砂白き
雄松が里の乙女子は
赤い椿の森陰に
はかない恋に泣くとかや
波のまにまに漂えば
赤い泊火懐かしみ
行方定めぬ波枕
今日は今津か長浜か
瑠璃の花園珊瑚の宮
古い伝えの竹ちく生ぶ島
仏の御手に抱かれて
眠れ乙女子やすらけく
旧制三高=京都大学の歌だが、親父は京大には行ってない。そもそも親父は高卒である。親父がうたっているのをちゃんと聞いたのは、案外初めてだったかもしれない。いい声だ。そういや、親父とカラオケに行ったこと、なかったな。
今度は「茶摘みの歌」を母親と手を合わせながらうたう。
あれに見えるは茶摘みじゃないか
ぽんぽん。
屈伸運動をし、母親とぽんぽんと手を合わせる。
あかねだすきに菅の笠