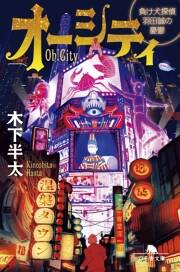『悪夢のエレベーター』などの悪夢シリーズや、『仮面ライダーリバイス』(テレビ朝日系列)の脚本で活躍する木下半太の、超高速クライムサスペンス『オーシティ』が、新たな顔で幻冬舎文庫になりました。そこで、冒頭を試し読み。
金と欲望の街「オーシティ」。ギャンブルシティとなった、かつての大阪―ー。泣く子も黙るこの街で、“負け犬探偵”の羽田誠、”死神”と呼ばれる刑事、拷問好きな殺し屋、逃がし屋の少女、命を狙われた娼婦…ワケありの面々が疾走する!
* * *
プロローグ
冷たい。
茶谷(ちゃたに)新一は金玉の冷たさに目を覚ました。
暗く、黴(かび)臭い地下室──。たぶん、地下室だ。後頭部を殴られ気絶しているあいだに、ここに運ばれたらしい。

地下室の真ん中にテーブルがある。茶谷はその上に仰向けに寝かされていた。両手両足が動かない。革のベルトでしっかり固定されている。
どうやら、このテーブルは食事をするためではなく人間を磔(はりつけ)にするために使うようだ。
気がかりなのは全裸にされていることと、金玉のひんやりとした感覚である。
誰に拉致られたのかは容易に想像がつく。スキンヘッドで全身刺青だらけの“耳切り茶谷”にこんな真似をする奴は、この街には一人しかいない。
チクショウ。俺の金玉はどうなってるんだ?
茶谷は首を折り、下半身を見た。金玉がどういう危機に晒されているのか確認したかったのだ。
クソッタレが。舌打ちが地下室に響く。縮れた陰毛と萎れたペニスしか見えない。
長い人生の中で、“最悪の一日”というものがある。茶谷にとって今日がその日だった。
朝、牛乳の賞味期限が切れていた。
レーズンを入れたコーンフレークと宮崎県名産の塩らっきょうを一粒食べるのが、朝の日課だ。茶谷の毎日は習慣に縛られている。潔癖症で神経質な性格のせいで何よりも習慣が崩れるのを恐れていた。四十五分のウォーキングのあと、熱いシャワーを浴び、新聞を読みながらコーンフレークと塩らっきょうを食べなければ、一日が始まらない。「精神を凌駕することのできるのは習慣という怪物だけなのだ」と言ったのは誰だったか。
思い出した。三島由紀夫だ。
とにかく日課をこなさなければイラついてしょうがないのだ。このまま仕事に行けば、切らなくてもいい耳まで切ってしまう。
コンビニへ買いに行くことにした。《牛乳を買う》と、三日前に手帳に書いたのに忘れていたなんて、我ながら信じられない。
マンションを出た瞬間、カラスに襲われた。真っ黒でデカい奴だ。「クエーッ」と高く鳴き、低空飛行で攻撃を仕掛けてきた。

茶谷は、のけ反った拍子によろめいて転び、シャワーを浴びたばかりで石鹼がほのかに香る身体でゴミ袋の山に突っ込んだ。腐った肉や魚や野菜の汁の臭いが全身を包む。
決めた。今日は全員の耳を切り落とす。そうでもしなきゃ、この怒りは収まらない。
茶谷の仕事は、闇金の取り立て屋だ。
数年前、この街は大きく変わった。幾つもの高級ホテルとカジノが建ち、世界中から金持ちと観光客と悪党が集まってきた。
ギャンブルにどっぷりと浸かったジャンキーたちは、利子のことなど微塵も考えず金を借りる。そこで必要になるのが、負債者にナメられない男だ。ジャンキーたちは揃いも揃って、「ないものはないねんからしゃーないやろ」と開き直る。
茶谷は奴らの耳を躊躇(ちゅうちょ)なく切り落とす。そうすれば、どんな屈強な男でも次の日には必ず返済する。強盗をしてでも金を用意する。もう片方の耳まで失いたくないからである。
負債者たちの耳を切りはじめてから自分がサディストだと知った。耳を切るときのシャクッと心地のいい音に、いつも股間が熱くなる。

茶谷は部屋に戻ってシャワーを浴び直し、半袖の赤いシャツを羽織った。仕事のときはいつも赤い服を着る。耳を切り落とすたびに返り血を浴びるからだ。
愛用のナイフをポケットに入れてマンションを出た瞬間に襲われた。
今度はカラスではなく、人間だった。
茶谷はひっくり返された亀のように首を伸ばし、地下室の中を見回した。
明かりは、入口近くの壁に掛けられた小さなランタンが一つだけ。そんなに広くはない。コンクリートの壁は所々で剥がれている。階段が見えた。古いビルの地下だろうか。
部屋の隅には、殺風景な室内に不似合いな高級オーディオセットが置いてあった。
アンプはマニアックな真空管式らしい。その横に赤いシャツが落ちている。ジーンズやトランクス、スニーカーもある。すべて茶谷の物だ。
二十歳でこの業界に入った。それから八年、数々の修羅場を潜ってきた。ナイフで刺されたこともあるし銃で脅されたこともある。
どんな相手にも退かないしビビらない。そのつもりだった……。
足音が聞こえた。誰かが階段を降りてくる。
茶谷は渾身の力を込めてもがいた。革のベルトが皮膚に食い込むばかりで、どうにもならない。
殺される。
いや、今から現れる相手が茶谷の想像している男だったら、殺すことすらしてくれない。
足音が止まった。一瞬にして、ぬめりとした空気が部屋の中を支配する。
茶谷は天井を眺め、ゴクリと唾を飲み込んだ。

これは未体験の悪のオーラだ。所詮、自分は小物なんだと一瞬で悟らされた。
「恐怖って、何やろうな?」
男が、ゆらりと茶谷の視界に入ってきた。
やっぱり……。絶望感にうちのめされる。
白いパナマ帽。ウェーブがかかった長い髪。高級な生地を使った白いスーツ。
この街の死神、愛染京太郎だ。
「真の恐怖って、一体、何やろうな?」
「あああ、あい、ぞぞぞ、ぞめ」
口が震えてうまく言葉が出ない。奥歯がガチガチと鳴ってしまう。
「借金がとめどなく増える恐怖もあれば」
「あいあいああいぞめさん、たたすけ」
「耳を切り落とされる恐怖もある」
愛染京太郎の伝説を耳にしたのは一度や二度ではない。悪の化身だと言う者もいれば、心酔した目でカリスマだと語る者もいる。
「た、たすけて」
「茶谷。お前は何が怖い?」
愛染が右手でパナマ帽を取った。
草食動物のような優しい目が現れる。薄い眉。女のように透き通った白い肌。街中の悪党を怯えさせている男は、近くで見ると驚くほど優男だった。
愛染の左手に手鏡が握られている。
「これは怖いか」
手鏡の中に茶谷の股間の様子が映った。
なぜ金玉が冷たかったのか、謎が解けた。答えは茶谷の股間の下に万力が仕込まれていたからだ。

「拷問のために特別作らせたテーブルや」
金玉がぴたりと万力に挟み込まれている。回転レバーをあと数回も回せば、金玉は完全に潰れてしまう。
『アイツに近づいたらアカン』
借金を取り立てたチンピラの言葉を思い出した。
『愛染という名前が聞こえただけでもダッシュで逃げたほうがええど』
そのヤクザは、右腕が肩の先から無かった。愛染と揉めて落とされたのだ。
「苦痛には限界があるが、恐怖に限界はないらしい。試してみよか」
愛染が真空管アンプのスイッチを押した。オレンジの明かりが静かに灯り、しばらくして馬鹿デカいスピーカーから聞いたことのある曲が流れてくる。
女性ボーカルが、イエスタデイ・ワンスモアと歌っている。
……カーペンターズだ。
なぜ、この曲をかける? 儀式的にかけているのか。
何にせよ、カーペンターズを聞きながら金玉を潰されるなんて洒落にならない。
「いつ聞いてもいい曲やな」
愛染がサビをハミングしながら近づいてくる。
恐怖が洪水のように全身を襲う。確かに恐怖に限りはない。
「待ってください! 俺がこんなことをされる理由を教えてください!」茶谷は背中を弓なりに反らせて絶叫した。
「お前が人の耳を切って恐怖を与えてたからや」
「えっ……それで、どうして愛染さんが?」
「だって俺は刑事やからな」愛染が万力のレバーを握りグイッと回す。
股間の下で、プチトマトを奥歯で嚙んだような音がした。
「がぎゃああああ」
ほ、本当に金玉を潰しやがった。下半身からせり上がってくる激痛に気を失いそうになる。
「こ……殺してやるからな……」茶谷は涙を流しながら愛染を睨んだ。去勢された屈
辱に全身がブルブルと震える。
「ぜひ殺してくれや」愛染が満面の笑みを浮かべた。「そのときは俺に真の恐怖を与えるのを忘れるなよ」
(つづく)
オーシティ 負け犬探偵羽田誠の憂鬱

泣く子も黙る「オーシティ」。巨大なギャンブルシティと化した、かつての大阪。落ちぶれた探偵の羽田誠は、街の死神と呼ばれる刑事・愛染から脅迫される。誰より早く“耳”を探せ。失敗したら地獄行き――。耳を追うのは、殺し屋、逃がし屋、娼婦、盲目の少女。ただの耳に、全員が命がけ!? 謎多すぎ、最後まで結末が読めない、超高速サスペンス!