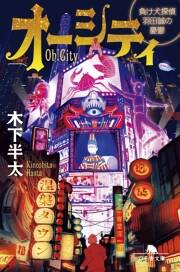金と欲望の街「オーシティ」。ギャンブルシティとなった、かつての大阪―ー。泣く子も黙るこの街で、“負け犬探偵”の羽田誠、”死神”と呼ばれる刑事、拷問好きな殺し屋、逃がし屋の少女、命を狙われた娼婦…ワケありの面々が疾走する!
木下半太の『オーシティ』。冒頭を試し読み。
* * *
第1章 負け犬探偵
1
別れた妻はカップラーメンが大好きだった。
「日本人が発明したものの中で二番目にすごいものがカップラーメンだと思う」
お湯を沸かしながら、別れた妻はいつも同じセリフを言った。
「一番目は何だよ」
「ウォシュレットよ」
一番目の答えはその日によって違う。前に訊いたときは“回転寿司”だった。でも、二番目のカップラーメンは不動なのだ。
「じゃあ、カップラーメンができるまで時間をあげるから」別れた妻は、カップラーメンにお湯を注ぎながら、これまたお決まりのセリフを言う。「私を愛してる理由を並べて」

「三分間ずっとだよね?」
別れた妻は嬉しそうに頷く。
この儀式にいい加減うんざりしていた。もちろん顔には出さなかったが、別れた妻はときに少女のようにわがままになる。
三分間は長い。苦痛にも等しい時間だ。必死で考え、彼女が喜びそうな理由を捻りだした。もし、三分間言い続けなければ、別れた妻は豹変してわめき散らす。
愛してる理由なんか一つしかない。“愛してる”からだ。
だけど、それで、許してくれるはずもない。
覚悟を決めて、愛している理由を並べた。
「君は俺がどれだけ遠くに離れていても、ずっと見ていてくれる。俺は君の視線を感じながら幸せに身を震わせるんだ。君は魔法使いさ。指一本で、俺を生かすも殺すも自由自在なのさ」
別れた妻は、歯が浮きそうに甘い言葉を聞きながら、うっとりと微笑んだ。
「人生の中で、三分間ぐらいは素敵な時間があってもいいでしょ」
「ビューティフル」
外国人観光客が頭の上で呟いた。デジカメで戎橋(えびすばし)の《グリコの像》を撮りまくっている。カウボーイハットを被った中年の白人親父だ。

「ガッデム!」
中年カウボーイが、ふいに転ぶ。
羽田誠はタキシード姿で、シャンパンの瓶を抱いたまま戎橋に寝転がっていた。顔中、ゲロだらけだ。中年カウボーイがつまずいたのは羽田の足だった。
今さっき、泥酔から目覚めたばかりだ。カジノで大負けをしてのヤケ酒。この街では、珍しい光景ではない。ちなみにシャンパンは、ブラックジャックのテーブルで隣に座っていたアラブ人が奢ってくれた。奴は大勝ちし、ブロンドと黒人の娼婦を両手に抱えてカジノの上にあるホテルへと消えていった。今頃はスイートルームで鼾(いびき)をかいて寝ているだろう。
中年カウボーイが顔を真っ赤にして、「ファック!」だの「シット!」だのと怒鳴り散らしていたが、羽田は無視して起き上がった。頭が痛くて割れそうだ。安いシャンパンほどたちの悪いものはない。アラブ人もどうせ奢ってくれるなら、まともな酒にして欲しかった。
タキシードのポケットをまさぐる。タバコも金もない。携帯電話も見当たらない。
最悪だ。寝ている間に盗まれたか……いや、カジノだ。《大黒(だいこく)グランド》のクロークに預けたままにしていたのを、大敗のショックで忘れていた。
クソッ。金もないのにカジノに戻るのかよ。
羽田はヨロヨロと歩きだした。半日近く、コンクリートの橋の上で眠っていたせいで、全身の関節が軋む。

戎橋を渡り、巨大なアーケードをくぐる。金曜の夜の《道頓堀ストリート》は、欲望を剥き出しにした観光客たちでごった返している。アーケード全体を覆うスクリーンに巨大なカニが現れた。《かに道楽》のコマーシャルだ。《道頓堀ストリート》は、ラスベガスのフリーモント通りのパクリで、三百万個の電球と数十台の高性能スピーカーを駆使し、歩行者の頭上で光と音のアトラクションが繰り広げられる。
ラスベガスのパクリはこれだけではない。道頓堀川の噴水ショーもある。BGMによって、噴水が生き物のように動く。曲のジャンルはクラシックから流行のJポップまで幅広い。もちろん一番人気は『六甲おろし』である。阪神タイガースが勝った日にだけ見ることができるアトラクションで、二千基のハイテク噴射装置が、黄色にライトアップされた噴水を力強く空に舞い上げる。けれど観光客たちは、噴水が目当てではない。興奮して暴徒化した阪神ファンが、噴水に飛び込む姿を見たいのだ。
この街は眠らない。どこのホテルのカジノも二十四時間、ぶっ通しで営業している。
昼も夜も金の亡者が街中をうろつき、一攫千金を夢見ては堕ちていく。
七年前。大阪市は負債が膨れ上がり、財政が完全に崩壊した。そこで、荒療治のカジノ導入。あっという間にラスベガスとマカオを抜いて、世界一のカジノタウンになった。道頓堀は三十億円をかけて《道頓堀ストリート》になり、グリコの看板はニューヨークの《自由の女神》のような巨大像《グリコの像》として生まれ変わった。両手と片足を上げた例のポーズでそびえ立っている。
カジノのおかげで世界中の金が集まり、“日本一借金のある街”が“世界一夢のある街”になった。ただ、凶悪犯罪の件数は、毎年うなぎ登りで記録を更新中だ。当初は、外国人観光客のために“オオサカシティ”と呼ばれていたが、ギャンブラーはみんな気が短い。いつの間にか省略されて、“オーシティ”となった。

羽田はこの街で、絵本探偵をしている。ペット専門や浮気調査専門の探偵と同じだ。
羽田は絵本しか探さない。三年前までは、行方不明になった人間を探すまともな探偵だったが、足を洗った。嫌気が差したのだ。失踪するからには何らかの理由がある。五人に一人は死体になっているし、たとえ生きていたとしても依頼人であるヤクザに引き渡さなければいけないことが大半で、その都度気分が滅入った。
ある日、羽田は自分の母親と変わらない年齢の女を探しだした。ヤクザが経営するキャバレーでジャズを歌っていたボーカリストだった。カジノで借金を作って金に困り、キャバレーの売上金を盗んで逃亡していた。
見つけ出したとき、女はマスカラが溶けた黒い涙を流しながら「この疫病神」と羽田を罵(ののし)った。女をヤクザに引き渡した三日後、ラブホテルで女は死体になっていた。体からは致死量のドラッグが検出されたと聞いた。
それ以来、羽田は“まともな探偵”から足を洗うことを決意した。
《大黒グランド》の前に着いた。オーシティで、一、二を争う大型ホテルだ。客室は三千八百室。一階と地下一階がカジノになっている。ホテル前の大黒様の巨大オブジェは道頓堀の《グリコの像》と並んでオーシティの名物である。
「こんばんは。今夜もご機嫌な夜になりそうですね」
黒人ドアマンが羽田に笑顔を浮かべ、流暢な日本語で挨拶をしてきた。どのカジノでも、ドアマンには日本語が堪能な外国人を入口に立たせている。海外からの観光客が多いし、日本人を使うよりも見栄えがいいからだ。

羽田の顔についているゲロを見て、ドアマンから笑顔が消えた。「お前はダメだ。入るな」厳しい口調になる。
「忘れ物を取りに来ただけなんだよ」羽田は大げさに肩をすくめてみせた。「携帯電話だ。あれがないと仕事ができない」
本当は携帯電話が戻ってきたところで仕事はない。依頼は先月が一件で、今月はゼロという悲惨な状態だ。
「入るんじゃない」
ドアマンが羽田の腕をつかんだ。業務用冷蔵庫みたいに体がデカい。その気になれば、日本人の平均的身長の羽田くらい一瞬で捻り潰せるだろう。
「これで勘弁してくれよ」羽田はタキシードのポケットからデジタルカメラを出してウインクした。戎橋で中年カウボーイが落としたものだ。「この一見何の変哲もないカメラにはとんでもない秘密があるんだ。何だと思う? これはCIAのスパイが潜入捜査で使っていたカメラなんだよね。凄くないか。オーシティには観光客を装ったスパイがうじゃうじゃいるのは知ってるだろ。もちろんCIAに興味がなければ、そのカメラを質屋に持っていけばいい。最新式だから言い値で買ってくれると思うぜ」
腕力のない羽田がこの街で生きていくには、口で相手を丸めこむテクニックが必要だ。
ドアマンが、しかめっ面で羽田の賄賂を受け取った。「まずトイレで顔を洗え。いいな」
賄賂を受け取るときの表情は世界共通だ。どの人種でも、必要以上に真面目な顔になる。ただし、鼻の穴が膨らんでいることに本人たちは気づいていない。
(つづく)
オーシティ 負け犬探偵羽田誠の憂鬱の記事をもっと読む
オーシティ 負け犬探偵羽田誠の憂鬱

泣く子も黙る「オーシティ」。巨大なギャンブルシティと化した、かつての大阪。落ちぶれた探偵の羽田誠は、街の死神と呼ばれる刑事・愛染から脅迫される。誰より早く“耳”を探せ。失敗したら地獄行き――。耳を追うのは、殺し屋、逃がし屋、娼婦、盲目の少女。ただの耳に、全員が命がけ!? 謎多すぎ、最後まで結末が読めない、超高速サスペンス!