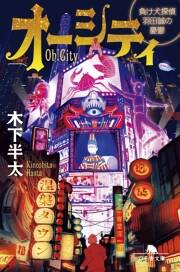金と欲望の街「オーシティ」。ギャンブルシティとなった、かつての大阪―ー。泣く子も黙るこの街で、“負け犬探偵”の羽田誠、”死神”と呼ばれる刑事、拷問好きな殺し屋、逃がし屋の少女、命を狙われた娼婦…ワケありの面々が疾走する!
木下半太の『オーシティ』。冒頭を試し読み。
* * *
羽田は回転ドアをくぐり、《大黒グランド》に入った。
スロットマシンの電子音、ルーレットが回転し玉が転がる音、客たちの悲鳴と怒号、BGMのハードロック。色々な音が混ざり合い、カジノに活気を与えている。フロアには異様な熱気が充満していて、あきらかに酸素が薄い。

《大黒グランド》のカジノの内装は、和のテイストを加えたゴージャスなデザインで人気を博していた。テーマは『黄金の国ジパング』。壁や柱は金箔を貼りつけたようなゴールドで統一されている。まるで、黄金の城に迷いこんだみたいだ。ルーレットの数字は漢字。スロットの絵柄には忍者や芸者のイラストを使っている。スシバーのカウンターもあり、いつでも一流の職人が握る寿司を味わえた。
羽田は、まっすぐ男子トイレに向かい、洗面台で顔を洗った。鏡に映る自分の顔を見て、吐き気が復活した。ボサボサの髪に、伸び放題の無精髭(ぶしょうひげ)。目の下のクマがひどい。頬もげっそりとこけている。
心なしか髪も薄くなってきた。まるでタキシードを着た落ち武者みたいだ。
いつから、こうなった? ゲンナリした。わかってる。妻と別れてからだ。
羽田はもう一度、激しく顔を洗った。ふと足元に目をやる。スロットマシンのコインが一枚落ちていた。そのコインを拾い、男子トイレを出る。
大股で、スロットマシンのコーナーへと向かった。
勝てるわけがないのはわかっている。ただの運だめしだ。ここは“世界一夢のある街”なのだ。
心臓がトクトクと鼓動を速めた。アドレナリンが全身を駆けめぐっている。トイレで拾ったコインでこんなにも興奮するなんて、末期のギャンブル依存症もいいとこだ。

『あなたのいいところは自分を負け犬だと素直に認める潔(いさぎよ)さよね。うん。慰め甲斐がある』
別れた妻の言葉を思い出して、羽田は一人で笑った。
三年前、真夜中の食卓で、羽田は妻に絵本探偵になることを告げた。
「依頼の絵本を探し出す?」妻はわざとらしく鼻で笑い、ほうじ茶を啜った。「本屋で新しいのを買えばいいじゃない。そもそもなんで絵本なのよ」
「現物だから価値があるんだ。子供のころに読んでいた絵本を取り戻したいって人は結構いるんだってば。小さいころ、絵本に自分の名前や落書きを書いた覚えがあるだろ」
「まあね。私は『モチモチの木』が好きだったわ。父親のライターでイタズラして燃やしちゃったけど」寝ているところを起こされたせいか、妻は不機嫌だった。「意外と絵本は捨てられないものなんだ。親戚の子供にあげたり、親にリサイクルに出されたり、図書館に寄付したものが、何十年後かに自分の元に戻ってきたら感動しないか」
実際に依頼人たちは涙ぐんで喜んでくれた。当然、こんな酔狂なことに金を出すのは金持ちだけで、バカ高い料金をふっかけても文句を言われたことはない。軌道にさえ乗ればおいしいビジネスなのだ。危険は無いし、何より「疫病神」と呼ばれることもない。
「いつまで続けるつもりなの」妻が哀れむような目で羽田を見た。
「そうだな……」先のことなど何も考えていなかったから、適当に答えることにした。
「俺が昔好きだった絵本が見つかるまでかな。『おおきなかぶ』って本知ってる?」
「知らない」
「大きなかぶをみんなで力をあわせて抜くんだ。“うんとこしょ、どっこいしょ”って掛け声をかけてね」
「だから知らないって」妻が深いため息をつく。
「俺、表紙のタイトルにマジックで書き足して『おおきなかぶとむし』にしちゃったんだ。母さんにむちゃくちゃ怒られたなぁ」懐かしさに胸が熱くなった。「子供のころの絵本が戻ってくれば誰だって嬉しい。こんな素敵な商売ないと思う」
妻はほうじ茶を飲むだけで、何も言わなかった。
その態度が気に食わなくて、羽田はつい余計な一言を発してしまった。
「君の昔の仕事よりマシだろ」
次の日、妻は家を出ていった。

2
携帯電話の着信音に叩き起こされた。
「うるせえな……」羽田は耳を塞(ふさ)ぎ、薄っぺらい枕に顔を埋めた。
臭い。加齢臭というやつだ。女っ気もなく、冷たいベッドに独り寝なんて、我ながら悲しくなる。
いつまで経っても携帯電話が鳴り止まない。こんなことなら《大黒グランド》のクロークに預けたままにしておけばよかった。
「寝かせてくれ」羽田は叫んだ。
隣の部屋からドンと壁を殴られた。古いマンションで壁が薄い。咳払いや、便所の水を流す音まで聞こえる。
アメリカ村のラブホテル街のど真ん中に、羽田が住んでいるマンションがある。大阪市の時代までは、“アメ村”と言えば若者の街だったが、オーシティになってからは外国人ギャングたちが流れ込み、一般人が気軽に立ち寄れないスラム街と化した。腐るほど乱立していた古着屋はことごとく閉店し、幾つものビルが廃墟となり、ジャンキーや娼婦たちの溜まり場となっている。
ゆえに、アメ村に残っているマンションの家賃はバカ安い。2LDKで三万円だ。借金まみれの羽田にはありがたいが、隣にドラッグの売人のジャマイカ人、その隣にはポン引きのメキシコ人が住んでいるので、とてもじゃないが快適な環境とは言い難い。
着信音がしつこい。
羽田は、ベッド脇の目覚まし時計を見た。午前二時三十五分─。こんな時間にかかってくるなんてロクでもない電話に決まっている。
立ち上がって携帯電話を探した。頭が痛い。今夜はしこたま飲んだ。芋焼酎の味のゲップが出る。トイレで拾ったコインで、奇跡的に勝ったのだ。と言っても、勝った額は一万円とちょっとで、居酒屋とスナックで消えてしまった。スナックはツケにしたから結果的にはマイナスだ。
ケータイはどこだ? タキシードのポケットにはなかった。またもやタキシードのまま眠ってしまっていた。せっかくの一張羅が皺くちゃになっている。
着信音を辿り、床にしゃがみ込んだ。あった。ベッドの下だ。
「死ね」画面は見ず、電源を切った。これで、ようやくグッスリと眠ることができる。
ベッドにダイブしようとした瞬間、窓ガラスが割れた。

羽田は、慌てて身を伏せた。一瞬で全身から汗が噴き出す。
最初は石かと思った。ガソリンの臭いと、瓶の欠片と、カーテンが燃えているのを見て、何を投げ込まれたのかわかった。
火炎瓶だ。パニックで動けなかった。もちろん、自分の家に火炎瓶を投げ込まれたのは初めての経験だ。羽田の部屋は二階にある。酔っ払いか、シャブ中の悪戯だろうか。
クローゼットに火が燃え移った。羽田の持っているすべての服が勢いよく燃えていく。
「羽田誠」
道路から聞き覚えのある声がした。
頼む、夢であってくれ。
「十秒以内に降りてこんかい。これ以上、俺の時間を浪費すんなよ。お前の時間と俺の時間の価値が同じだと思うな。ダイヤモンドと鼻糞ぐらい差があるねんぞ」
愛染京太郎だ。最悪にもほどがある。
羽田は、このまま焼け死のうかと本気で悩んだ。
「絵本探偵やと? 相変わらず人生をナメきった野郎やな」
愛染が、たこ焼きをサルサソースにつけながら露骨に鼻で笑った。別れた妻とまったく同じ反応だ。
羽田と愛染は、アメ村の居酒屋《アミーゴ》の一番奥のテーブルに座っていた。
《アミーゴ》は大阪市時代、たこ焼きがウリの《味穂》という店だった。一階の路面でたこ焼きを売り、狭い階段を上った二階が居酒屋スペースで、串カツやおでんも出して朝まで賑わっていた。特にたこ焼きは、ソースではなく出汁につけて食べる明石焼きスタイルで数多くのファンがいた。しかし、オーシティになってから、《味穂》が入っているビルがメキシコギャングに乗っ取られ、以来店名は《アミーゴ》に変わり、出汁もサルサソースになってしまった。串カツやおでんも、タコスやチリビーンズになった。ただ店内は、和食の内装のままなので思いっきり違和感がある。
愛染はお洒落なゲイに見えなくもない。パナマ帽といい、スーツといい、エナメルの靴といい、全身を白一色でキメている。肌までもが白い。どこかエレガントな空気さえ漂っている。地中海の避暑地から抜けだしてきたような出立ちだ。
ただ、氷のようなその視線で射すくめられると、喉元に鋭利な刃物を突きつけられたような錯覚に陥ってしまう。
美しすぎる死神だ……。

(つづく)
オーシティ 負け犬探偵羽田誠の憂鬱の記事をもっと読む
オーシティ 負け犬探偵羽田誠の憂鬱

泣く子も黙る「オーシティ」。巨大なギャンブルシティと化した、かつての大阪。落ちぶれた探偵の羽田誠は、街の死神と呼ばれる刑事・愛染から脅迫される。誰より早く“耳”を探せ。失敗したら地獄行き――。耳を追うのは、殺し屋、逃がし屋、娼婦、盲目の少女。ただの耳に、全員が命がけ!? 謎多すぎ、最後まで結末が読めない、超高速サスペンス!