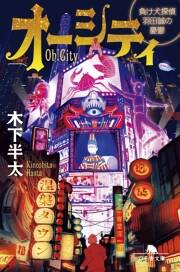金と欲望の街「オーシティ」。ギャンブルシティとなった、かつての大阪―ー。泣く子も黙るこの街で、“負け犬探偵”の羽田誠、”死神”と呼ばれる刑事、拷問好きな殺し屋、逃がし屋の少女、命を狙われた娼婦…ワケありの面々が疾走する!
木下半太の『オーシティ』。冒頭を試し読み。
* * *
茶谷がホッとしたのがわかった。
王小蘭は茶谷の女だ。中国人の娼婦で、《涅槃(ねはん)タウン》と呼ばれる娼婦街の売春宿《百足屋》にいる。茶谷が借金のカタに無理やり自分の女にしたのは、だいぶ前から知っていた。

茶谷が“耳”を預けるなら王小蘭だ。人から恨みを買いまくっている茶谷は誰も信じていない。
「アイツはもう俺の女じゃねえ。とっくの昔に別れたんだ」茶谷が投げやりに言った。
嘘をついているのが丸わかりだ。茶谷のようにプライドの高い男が自ら「女と別れた」と宣言するわけがない。もし、言うならば「俺が捨てた」のはずだ。どうやら本当のことを言うしかなさそうだ。
「じゃあ、殺されてもいいんだな」
「いいわけねえだろ」茶谷が、またナイフを出した。潰れた金玉の激しい痛みが響いたのか、顔を歪める。
「愛染が王小蘭の命を狙っている」
茶谷がガタガタと震えだした。「俺のせいだ……俺が……」
「どうして、愛染は王小蘭を追っているんだ?」
茶谷は、股間を押さえたまま答えようとはしない。
「茶谷、教えてくれ。情報がないと王小蘭を助けることができない」
「小蘭を助けてくれるのか」
「そのために探している」
助ける気など、更々ない。愛染の探している“耳”さえ見つかれば、王小蘭がどういう目に遭おうと知ったこっちゃない。
茶谷が、言おうかどうしようか迷っている。
「こうしてる間にも、愛染がオーシティ中を探し回ってるぞ」
「わかった。教えるよ」
ダメ押しが利いた。羽田は手帳とペンを出した。
「ここじゃ、マズい。屋上に行こう」
「大丈夫。オナラの音で誰にも聞こえない」
隣のオナラは徐々にボリュームが上がってきている。
「でも……」茶谷が口ごもる。
「一秒でも早いほうが、王小蘭が助かる確率は上がる」
茶谷が覚悟を決めたように頷き、声を潜めて話し出した。「一カ月ほど前、あるインド人の耳を切り落としたんだ」
「インド人?」
「堀江に住んでいる変人でよ。まだハタチそこらで賭け将棋にハマって、多額の借金を作ってしまったんだ」
オーシティになって色んな国の人間が集まってきているが、さすがに将棋をする外国人は珍しい。
「そのインド人は日本に何しに来たんだ」
「どうも留学生らしい。いつまで経っても金を返しやがらねえから右耳を切り落としてやったんだ。いつもなら耳はその場で捨てるか踏んづける。だが、持って帰ったんだ」
「なぜ?」
「親が金持ちじゃねえかと思ったからだよ。高級マンションに住んでるし、車はポルシェだ。靴も生意気に《ジョン・ロブ》を履いてやがる。誰だって大富豪の息子かと思うだろ」
「だったら、借金なんかしないだろ」
「甘いな。金持ちの親でも厳しいのはいる。仕送りの金をギャンブルに使ったとバレたら、勘当されるかもしれないだろ。そうなってくると、親に言えず借金に走る。でも、元々、金銭感覚がおかしいガキだから歯止めが利かねえ」
「耳を人質にしたのか」
茶谷がニタリと笑った。「冷凍して保存しといてやるから、親に連絡しろと言ったんだ」

「親の代わりに、愛染が来たんだな」
「最悪だよ。一千万は引っぱれると思ったのに……。まさか、あのインド人のガキが愛染に泣きつくなんて予想外もいいとこだったぜ」
「その耳は、今、王小蘭が持ってるのか」
「持っているかどうかはわからねえ。預かってくれって言って渡しただけだから、どこかに隠しているかもしれないな。知ってたら、金玉を潰される前にゲロってるよ」
「どんな耳だったか詳しく教えてくれ」
「どこにでもあるような普通の耳だよ。色んな耳を切り落としてきたけど、どれも同じようなもんだよ。違いがあったとしても耳たぶがデカいくらいだな」
「耳は何色だ」
「薄い茶色だ」
「他に特徴は?」
「ピアスがついてたな」
「どんなピアスだ」
「しつこいなお前。どこにでも売ってるようなプラスチックのやつだよ」
「形は?」
「星形。あんまり憶えてねえけど、銀色だったと思う。あのインド人のガキ、耳を切ったら内股でしゃがみこんでメソメソ泣きだしてたな」
「ありがとう」羽田は手帳を閉じた。これ以上、聞くことはない。
「何だよ、もういいのか」
「ああ。王小蘭を助けに行かないと」
「そうか……」茶谷が、寂しそうに口をへの字に結んだ。「おめえも金玉を潰されないように気をつけろよ」
「わかってる」
そうならないように、今、ここに来ているのだ。
「羽田は、どこの生まれだ」
「岐阜だ」
「俺は、宮崎だ。高千穂って知ってるか。いいとこだぞ。五ケ瀬川の真名井の滝を見せてやりたいよ。綺麗なんてもんじゃない。あそこは神様が降りてくる場所だ」茶谷がウットリと目を細めた。
「オーシティとは、大違いだな」
「この街には神も仏も近づかない」茶谷の目から光が消える。「所詮、俺の金玉は潰れる運命だったんだよ」

4
久しぶりに《涅槃タウン》に来た。
羽田は車を降り、辺りを見回した。昼前だというのに活気で満ち溢れている。世界中からスケベ心丸出しの男たちが集まってきたのだ。
光り輝く場所の裏には、必ず闇がある。
オーシティになってからの浄化運動で、観光地区に近い飛田新地(とびたしんち)はなくなった。あぶれた娼婦たちは、大阪市九条にあった松島新地に集まり、涅槃タウンを作った。西日本で一番の武闘派指定暴力団《鳴海(なるみ)会》が街を仕切り、警察もうかつには手を出せない。
さびれていた松島新地は生まれ変わり、男たちのディズニーランドになった。

ここには、ありとあらゆる女が集まっている。アジアン、白人、黒人、スパニッシュ、ロシアン、ラテンと世界中の女が男を誘う。
みなと通り沿いの神社の横に涅槃タウンの入口がある。カジノが固まっている梅田や難波からも、タクシーを使えば十五分もかからずに来れる便利な距離だ。
まず、入口でチケットを購入しなければ涅槃タウンの中に入ることはできない。
一キロ四方の歓楽街を、金網のフェンスが囲んでいる。入場制限のためと、女を買わないで帰る見物客を防ぐためだ。
羽田はチケットを買って、ゲート前に並んだ。一斉に視線が羽田に集中する。タキシードを着ているのはもちろん羽田だけだ。
すげえな、こりゃ。 観光客の列から悶々(もんもん)とした性欲が漂っている。みんなやりたくてやりたくてしょうがないのだ。たぶん、ここにいる男のうち、冷静なのは羽田一人だけだろう。羽田は女に興味がない。妻と別れてから性欲がピタリと止まってしまったのである。夢精すらしなくなった。
別れた妻は性欲旺盛だった。セックスは、朝と夜にした。生理の日以外は毎日だ。妻のことをセックス中毒かと疑ったこともある。
性欲だけではなく、食欲と睡眠欲も人並み外れていた。イタリアンレストランでカルボナーラをおかわりする女は、別れた妻ぐらいだ。まるで、つけ麺でも食べるかのようにペロリと平らげる。
あと、どこでも寝ることができる女だ。特技と言ってもいい。電車やバスは当たり前、自転車の運転中に居眠りしてドブにはまったこともある。
別れた妻はエネルギーの塊だった。誰よりも喜怒哀楽が激しく、羽田を困らせた。だから妻のいない家は、静かすぎて困る。
ゲートを潜り、《涅槃タウン》の中に入った。まさに芋の子を洗うような賑わいだった。
あらゆる人種の男たちが鼻息荒く、そして、少年のようにはしゃいでいる。
昭和のノスタルジックな雰囲気と、アジアの猥雑さが絶妙にミックスされた街並みだ。

町屋の玄関に、ピンクや紫の妖しい照明でライトアップされた女の子たちが笑顔で座っている。玄関先に客引きの婆さんがいて、女の子から観光客に話しかけることはできない。観光客は気に入った女の子を見つけたら、婆さんと値段や時間の交渉をするシステムになっている。
売春宿のほかに飲食店や屋台も充実していた。特に屋台は、《涅槃タウン》のもう一つの名物で、屋台だけを目当てにやってくる観光客も少なくない。人気は、本場の中国人や台湾人の料理人が腕を揮(ふる)う点心の屋台だ。白人の団体が、水餃子、小龍包、焼売、ちまき、揚げパンをアテに、老酒で顔を赤くして陽気に騒いでいる。選りすぐりのいい女と、うまい飯に、酒。涅槃タウンは男の天国だと海外のメディアでも取り上げられていた。
屋台からうまそうな焼き豚の匂いが漂ってきた。ビールと焼き豚。たまらない組みわせに喉が鳴る。誘惑を振り切り、《百足屋》へと急いだ。
「疫病神が何の用や……」《百足屋》の客引き婆さんが羽田の顔を見てブツブツと呟いた。
(つづく)
オーシティ 負け犬探偵羽田誠の憂鬱の記事をもっと読む
オーシティ 負け犬探偵羽田誠の憂鬱

泣く子も黙る「オーシティ」。巨大なギャンブルシティと化した、かつての大阪。落ちぶれた探偵の羽田誠は、街の死神と呼ばれる刑事・愛染から脅迫される。誰より早く“耳”を探せ。失敗したら地獄行き――。耳を追うのは、殺し屋、逃がし屋、娼婦、盲目の少女。ただの耳に、全員が命がけ!? 謎多すぎ、最後まで結末が読めない、超高速サスペンス!