
第170回直木三十五賞候補作品に選出された小説『まいまいつぶろ』。この小説の第一章を特別公開いたします。
* * *
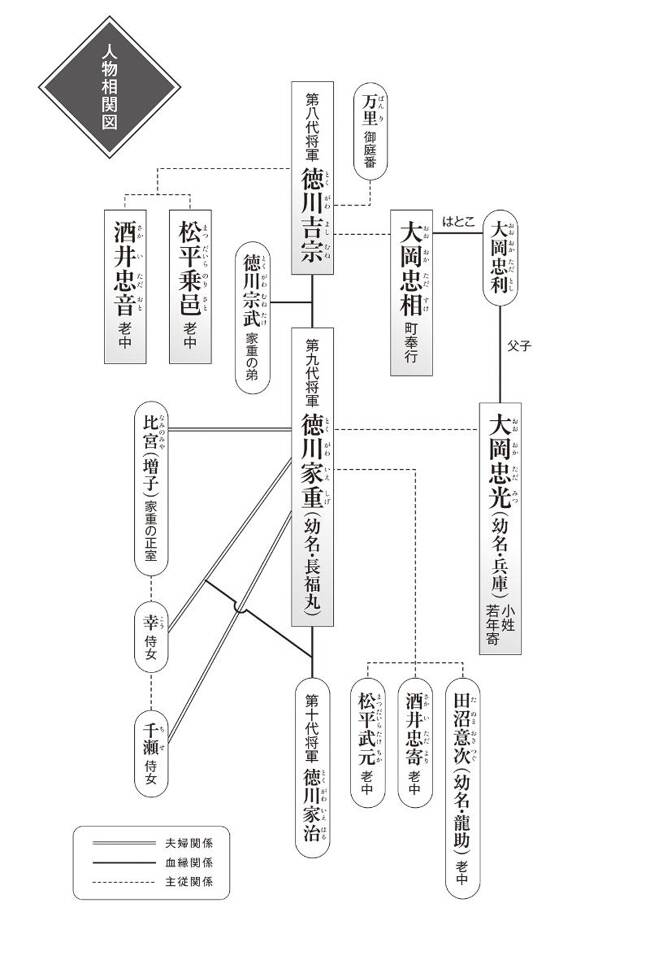
「長福丸様の御言葉を聞き取る少年が現れたのです」
江戸町奉行、大岡越前守忠相は江戸城中奥で四半刻ほど、上臈御年寄の滝乃井を待っていた。
滝乃井はかつて八代吉宗の嫡男の乳母を務めていた。そのため御台所に次ぐ権勢を持ってしかるべきところ、吉宗がまだ世継ぎを定めていなかったので、それほど重んじられてはいなかった。
「ああ、越前殿。お待たせしてしもうた、お許しくださいませ」
歳は忠相と同じく、四十半ばといったところだろうか。それ以外に忠相は滝乃井とのあいだに何の接点も見出せなかった。もちろんこれまで会ったこともなく、日常大奥から出もしない奥女中が自らの詰所に侍を招いて対面するとは、異例中の異例だった。
「それがしは構いませぬが、どのようなご用件でございましょう」
「ええ。越前殿のご高名は妾とて、よう存じております。上様の御信任の篤いこと、お人柄の清廉であられること……」
忠相は苦笑して滝乃井の口を止めさせた。さすがに滝乃井も気づいたようで、一つ息を吸った。
「今日は他でもない、長福丸様の御事でございます」
「これは、これは。それがしなどがお聞きして良いことでございますか」
長福丸とは滝乃井が乳母をしていた、十四になる吉宗の嫡男である。明年には元服するといわれており、その後は次の将軍として江戸城西之丸の主となる。
だが長福丸はそれに相応しい扱いを全く受けていなかった。つまり、誰も長福丸が将軍継嗣になるとは信じていない。なぜなら長福丸の身体には重い病があり、片手片足はほとんど動かすことができず、口をきくこともできなかったからだ。
「越前殿は長福丸様の御姿を拝したことがおありであろう。歩くには足を引き摺っておられ、乳母を務めた妾でさえ、お言葉がよう聞き取れませぬ」
忠相は合いの手を入れることも憚られ、押し黙っていた。
七年前、忠相は四十一歳という若さで江戸町奉行に任じられた。それからは小石川に養生所を作り、町火消を編成し、諸色の値を安定させるため、江戸で流通する金の価値を上げることに心血を注いできた。だがどれも一朝一夕とはいかず、世に言われる享保の改革も八年になろうとしている。
その改革を手伝う忠相は、たしかに吉宗から身に余る信頼を得ているが、将軍継嗣については聞かされたことがない。禄高二千石にすぎない忠相は、将軍家の家政に関わるような身分ではないのである。
「越前殿」
「はあ」
「長福丸様の御言葉を聞き取る少年が現れたのです」
「え……」
忠相は我にもなく絶句してしまった。長福丸には幾度か拝謁したことがあるが、声はあとえの混ざった音にしか聞こえず、首を動かすのでようやく是か非かが分かるだけである。麻痺で引き攣れた顔は表情にも乏しく、暗い印象しか残らなかった。
「それはまた。まことでございましょうか」
「ええ。でなければ越前殿にわざわざおいでいただきませぬ」
と言われても、忠相にはその訳こそ分からない。
滝乃井は勿体ぶって咳払いをした。
「長福丸様のお言葉を聞き取ったその少年、名を大岡兵庫と申して、越前殿の遠縁にあたりますのじゃ。ご存知あられぬか」
「大岡、兵庫。はて」
忠相は首をかしげた。大岡家は忠相の高祖父が家康に仕えたが、曽祖父も祖父も、父もそれぞれの代で分家している。当代、叔父や甥あたりまでなら顔も分かるが、それより広がると名も覚束ない。
「ふむ、左様であられましょうな。大岡兵庫は、越前殿の御祖父様の弟の血筋とか。禄高わずか三百石ゆえ、ご存知ないのも無理からぬこと」
「祖父の弟……。はとこの筋にあたりますか」
はとこの子か、孫だろうか。帰って誰に尋ねようかと、つい妻の顔を思い浮かべた。
しかし大奥の上臈御年寄がそこまで調べをつけているとは、根も葉もない噂の先走りではなさそうだ。
「そこでじゃ、越前殿。そなた様にはとくと、その者に言い聞かせてもらいたい。決して出過ぎた真似をいたさず、身の程を弁えるようにと」
「は? それはまた、何ゆえでございます」
「多少のことは目を瞑る。兵庫は長福丸様の小姓に取り立てます」
「め、滅相もない。三百石の小倅でございましょう」
忠相はつい声が大きくなった。三百石といえば御目見得も許されぬ少禄で、小姓になれる家柄ではない。そもそもあの長福丸の言葉を聞き取ることができるなど、とても真実とは思えない。
だが滝乃井は細い眉を吊り上げて忠相を睨みつけた。
「あの者の耳は真実じゃ。兵庫に会うた後の長福丸様の嬉しそうなお顔を、そなたは見ておらぬではないか。偽りだとてかまわぬ。一度でも長福丸様にあのようなお顔をさせてくれた者じゃ、生まれなどはどうでもよい。あれほどの忠義者はおりませぬぞ」
忠相は唖然とした。滝乃井の頬を涙が伝い落ちていた。
















